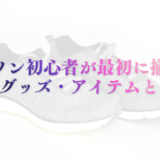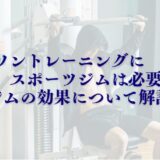マラソンの練習は順調でしょうか?
走ることを続けていくとマンネリ化することで飽きてしまったり、身体の特定の箇所に負担が集中することで腰・膝・足首といった関節を痛めてしまう可能性もあります。
飽きる・故障によるトレーニング中断リスクを抑えつつ、マラソンの成績向上を狙いたい方にとってクロストレーニングはオススメです。クロストレーニングとは、簡単に言えばマラソン以外の練習を取り入れることで、走ること以外でマラソンに必要な心肺機能や筋力向上を図るトレーニング方法です。
フルマラソンのように長距離を走る大会に出る場合、走るトレーニングが最も効果的であることは想像出来ますが、長距離を走る練習ばかりを続けてしまうと特定の筋肉・関節に負担が集中し故障のリスクが高くなります。そんな時にクロストレーニングを取り入れることで、負担の集中を避け、故障の予防に繋がります。
また、異なる運動はマンネリ化を防ぎ、飽きることによるモチベーション低下を予防することにも繋がります。
この記事では、ランナーにおすすめのクロストレーニング・メリット・注意点・ポイントなどを詳しく解説します。ぜひ参考にして下さい!
クロストレーニングとは?

クロストレーニングとはマラソン能力向上のために、他の運動をトレーニングとして取り入れる方法です。マラソン能力を向上させるには走ることが一番ですが、走ることだけを続けてしまうと特定の筋肉や関節に負担がかかり過ぎてしまい、故障の原因になります。また、走ることだけを続けると飽きてしまい、走るモチベーションが下がってしまうこともあります。
しかし、故障や飽きによるマラソントレーニングの中断リスクを抑える方法としてクロストレーニングが紹介されています。
マラソン能力向上のためのクロストレーニングとしてサイクリング・水泳・筋トレ・ヨガなどが主に紹介されており、これらのスポーツは心肺機能の向上や筋力・柔軟性の向上に繋がり、結果としてマラソン能力向上にも繋がります。
クロストレーニングは、自身の体力や興味関心のあるものを選ぶことが大切です。そして、徐々に負荷を高めていくようにしましょう。
クロストレーニングのメリット
心肺機能の強化
ランナーが行うクロストレーニングの目的は心肺機能の向上が多いです。心肺機能は自転車や水泳などの有酸素運動を取り入れることで、走らなくても向上することが出来ます。
関節を痛めて走ることが出来ない時は自転車や水泳を代わりに行うことで関節の負担を少なくしながら心肺機能の向上トレーニングが出来ます。
筋力強化
走ることだけを続けると走ることに特化した筋肉ばかりが強くなっていきます。一見、走ることに特化した身体として良いように感じますが、筋肉の成長がアンバランスになると姿勢の変化や関節の負担増加などにより故障の原因になったり、パフォーマンス低下の原因になったりします。
トレーニングには「全面性の原則」というものがあり、全身の筋肉をバランスよく鍛えることは身体のパフォーマンス向上やケガの予防に繋がります。ケガにより走ることが出来ない期間が出来ないように、補強運動として全身を鍛える筋トレなどを取り入れることが推奨されています。
ケガを予防
走り続けることによる故障は、特定の筋肉や関節に負担が集中することで生じることが多いです。実際に筆者も走り過ぎで、膝や腰を痛めて1~2カ月まともに走れなくなった期間があります。
走るということは、一瞬宙に浮いて片足で着地する行為の連続であり、足が着地する際は体重の3~5倍の負荷がかかると言われています。着地の衝撃を繰り返すことで特定の筋肉・関節にダメージが蓄積しケガ・故障の原因になることもあります。
別のスポーツで負荷を分散、全身の筋肉を鍛えることでケガを予防することが出来ます。
疲労回復・リフレッシュ効果
マラソンというスポーツは走り続けるという同じ動きを繰り返すスポーツの代表ともいえます。そのため、身体の特定部位に疲労が蓄積したり、飽きによるモチベーション低下によるトレーニング中断リスクが上がってしまいます。
そのため、別のスポーツを取り入れることで心身のリフレッシュになり、トレーニング中断リスクを抑えることが出来ます。
ランナーにオススメのクロストレーニング
サイクリング

自転車(サイクリング)はランナーのクロスレー二ングの定番の1つです。ロードバイク・クロスバイクなどでサイクリングをしたり、ジムなどでエアロバイクをすることによる長時間の有酸素運動は心肺機能の強化に繋がります。
また、自転車は走ることに比べて関節の負担が少ないことでも有名であり、関節の故障により走れない時に代わりに自転車をすることで心肺機能を向上させることも出来ます。さらに、走る時の筋肉に加えて、別の筋肉も鍛えることに繋がるため、全身の筋肉をバランスよく鍛えることにも繋がり、故障を防ぐ効果も期待出来ます。
心肺機能を向上させたい場合は、坂道を昇ることをオススメします。自転車の平坦は、自転車のトレーニングを積んだ人でなければ心肺に負担をかけることは難しいです。しかし、坂道を昇ることで自転車のプロでなくても自然と心拍数は上昇し、息切れが生じ、心肺機能の向上が期待出来ます。
暖かい時期はロードレーサー、寒い時期はランナーとして2つの持久系スポーツを季節ごとに楽しんでみてもいいかもしれませんね。
水泳

水泳は心肺機能の向上、全身の筋肉を使うことで有名なスポーツです。水による浮力があるため、関節の負担を大きく減らしながら、全身の筋肉を用いて、心肺機能の向上も期待出来ます。水泳をするにはプールが必要であり、近所に泳ぐ環境が無い人には難しいため、誰でも出来るわけではありませんが、泳ぐことが出来る環境にいる人は水泳はオススメのクロストレーニングです。
また、泳ぐだけでなく水の中を走ったり、スクワットなどの筋トレをすることで関節の負担を減らしながら水の抵抗により筋肉に負荷をかけることで筋力強化にも繋がります。
筋トレ

マラソンのための補強運動として筋トレは多くのランナーが取り入れているクロストレーニングです。筋トレをすることで全身の筋肉のバランスを整えて故障・ケガを予防することが出来ます。
しかし、筋トレもやり方を間違ってしまうと故障・ケガの原因になる可能性があるため以下のポイントを抑えておいて下さい。
1.正しいフォームで行う(誤ったフォームは関節を痛める可能性があります)
2.高負荷の筋トレではなく、低負荷・高回数を意識する(低負荷・高回数で筋トレをすることで有酸素運動に特化した筋肉を作ることが出来ます)
3.負荷は徐々に増やす(いきなり負荷を上げる過ぎると故障の原因になります)
4.筋トレの方法と鍛える筋肉を理解しバランス良く鍛える(やみくもに筋トレするのではなく、筋トレ方法と鍛える筋肉を理解することが大切です)
 | 青トレ 青学駅伝チームのコアトレーニング&ストレッチ/原晋/中野ジェームズ修一【3000円以上送料無料】 価格:1540円 |
 | 科学で鍛える! 筋トレ超大全 最新理論で理想の筋肉をつくる【電子書籍】[ 今古賀 翔 ] 価格:1980円 |
登山

足場の悪い坂道を昇ることは、走らなくても歩くだけで以外と心拍数が上昇します。登山のように山を登り続けることは、筋力強化・心肺機能の向上に繋がります。
また、山登りで自然に囲まれることは気分をリラックスさせる効果もあるため、登山もクロストレーニングとしてオススメされています。
ヨガ

ヨガは身体の柔軟性を向上、インナーマッスルの強化によりパフォーマンス向上が期待出来ます。
柔軟性向上による関節の可動域が広がることで走るフォームのパターンを増やすことが出来ます。また、筋肉の柔軟性向上は筋肉内の血管が拡がりやすくなる効果もあり、走っている時の筋肉への血行が促進されやすくなります。その結果、疲れにくくなりマラソンのパフォーマンス向上に繋がります。
クロストレーニングの注意点

クロストレーニングの大きなメリットは、負荷の分散によるケガ・故障のリスクを減らすことです。そのため、クロストレーニングで無理をしてケガをしてしまっては本末転倒です。
普段とは違う動きになるため、始めからハードな動きをすると筋肉を傷めることに可能性があります。最初は楽しむレベルから始め、徐々に負荷を高めていくようにしましょう。
また、運動後のストレッチ・マッサージなどによるケアも怠らないようにしましょう。
クロストレーニングを最大化するポイント

クロストレーニングの効果を最大化するためには、以下のポイントを意識して行いましょう。
知識を身に付ける
クロストレーニングを適切に行うには、そのスポーツの正しい知識を身に付けることが大切です。正しい知識を身に付けて正しいフォームで行うことでケガを予防したり、期待出来るトレーニング効果を理解することでトレーニングプランのバランスをとることが出来ます。
スポーツによる心身の負荷を理解していないと、身体の特定の箇所に負担が蓄積し故障のリスクが上がってしまいます。自身が行うクロストレーニングの知識は最低限は勉強しておきましょう。
目的を決める
クロストレーニングで心肺機能・筋力・柔軟性の何を向上させるのか目的意識をはっきりもっておきましょう。心肺機能を向上させたいのに、ヨガを選択することは目的と手段がマッチしていません。
スポーツの特性を理解し、目的を決めることでクロストレーニングメニューを自身で調整することが出来ます。
一貫性

クロストレーニングは単発では効果が継続しません。トレーニング効果を継続させるためには、クロストレーニングの継続が大切です。そのため、クロストレーニングをトレーニングプランに取り組み、無理なく継続することがポイントです。
 【風を切る日々!】
【風を切る日々!】